主婦で業界未経験の方が会計事務所への転職を検討する際に、まず知っておきたいのが会計事務所の仕事内容と人手不足の現状です。
本記事では、会計事務所での主な業務内容や、人手不足が起きている背景と今後の展望について解説します。さらに、雇用形態ごとの働き方やリモートワークの状況、子育てと両立しやすい職場かどうか、そして小規模事務所と大手事務所の違いについても、最新データや実例を交えて分かりやすく紹介します。転職を検討する際の判断材料にぜひお役立てください。
会計事務所での主な業務内容
会計事務所の職員は、企業や個人事業主の経理・税務をサポートする幅広い業務を担当します。例えば以下のような仕事があります。
- 記帳代行・データ入力
顧客企業の会計帳簿を預かり、会計ソフトを用いて仕訳入力や試算表作成などを行います。正確な帳簿管理によって経営状況を把握できるよう支援する重要な業務です。 - 決算書類の作成補助
月次・年次決算の際に、貸借対照表や損益計算書といった決算書類の作成を補助します。試算表をもとに数値を集計し、税理士の指示のもと必要な書類を準備します。 - 税務申告の補助
法人税や所得税、消費税の申告書作成をサポートします。領収書や請求書などの原始資料を整理し、申告に必要なデータをまとめます。年末調整の書類チェックや源泉徴収票の作成、法定調書の準備なども日常的な業務に含まれます。 - 顧客対応・相談業務
顧客からの問い合わせ対応や来客時の応対も会計事務所の仕事の一部です。電話やメールで経理・税務に関する質問に答えたり、資料の受け渡し対応をしたりします。小規模事務所では直接顧客先へ訪問して経営者と打ち合わせを行うケースもあります。
これらの業務を通じて、経理・会計や税法の専門知識を実践的に身につけることが可能です。
未経験から入社した場合でも、最近の会計事務所では新人研修やマニュアル整備が進んでおり、多くの事務所で丁寧に仕事を教えてもらえる環境があります。使用する会計ソフトは弥生会計やTKC、オービック(勘定奉行)など様々ですが、実務の中で操作に習熟することで市場価値の高いスキルとなります。

なぜ会計事務所は人手不足なのか? ~現状の背景~
近年、会計事務所でも人手不足が深刻化していると言われます。その主な理由として、以下のような要因が指摘されています。
- 若手人材の減少(税理士試験受験者減)
税理士や会計士など専門資格を目指す人自体が減っています。実際、税理士試験の受験者数は2005年(平成17年度)の56,314人から2020年(令和2年度)には26,673人と半減しました。難関資格に長い時間を費やすことへの不安や、他分野にもスキルを広げたい若者の志向転換が背景にあります。
その結果、会計事務所で働こうとする新卒・若手が減少し、業界全体で後継人材が不足しています。 - 高齢化とベテラン世代の引退
資格保有者である税理士・会計士の平均年齢は60歳代に達しており、今後ベテラン層の大量引退が見込まれます。平成期に急増した税理士事務所が現在も存続しているように、高齢の所長が率いる事務所が多く、世代交代が進んでいません。
一方で新規参入が少ないため、年齢構成のギャップが人手不足に拍車をかけています。 - 業務量の増加
働き方の多様化により、フリーランスや個人事業主として働く人が増えたことで税務申告を必要とする顧客が増加しました。毎年の税制改正や中小企業の経理ニーズの高まりもあり、会計事務所に求められる業務量が拡大しています。
その一方で人員が増えなければ、一人当たりの負担が重くなり慢性的な人手不足に繋がります。 - 待遇面の課題
給与水準の低さも人材確保を難しくする一因です。令和2年の統計では、会計事務スタッフの平均給与は他業種と比べて高いとは言えない水準でした。高度な知識を要する割に賃金が見合わないと感じる人も多く、優秀な人材ほど一般企業の経理職など待遇の良い職場へ流出しやすい傾向があります。
待遇改善が進まないまま業務だけが増えると、離職率が高まりさらに人手不足が深刻化します。 - AI・クラウドへの対応と不安
業界のデジタル化の波も人手不足に影響しています。近年クラウド会計ソフトの発達により仕訳の自動化が可能となり、従来は会計事務所に依頼されていた記帳代行業務の需要減少が懸念されるようになりました。このため、「将来AIに仕事を奪われるのではないか」という不安から資格取得を敬遠する動きもあります。
一方で、AIやITに精通した人材が不足しており、特に中小規模の事務所ではAI技術の知識を持つスタッフが顕著に不足しているとの調査結果もあります。新しい技術への対応が求められる中で、従来型のやり方から脱却できず人手不足に拍車がかかるケースも見られます。
以上のように少子高齢化による人材プールの縮小と業務需要の拡大・多様化が同時進行していることが、会計業界の人手不足の根本要因です。この状況により、現場では一人ひとりの業務負荷が増大し、新規顧客への対応が難しくなるなどの弊害も生じています。
人手不足が続けば職員のオーバーワークから離職が進み、さらに人手が足りなくなるという悪循環に陥りかねません。
 アドバイザー (公認会計士)
アドバイザー (公認会計士)会計事務所は本当に人手不足が続いているので、未経験者でもきちんと努力をしている人材は採用したいニーズが強いと思います。
多様な雇用形態とそれぞれの働き方・待遇
会計事務所では様々な雇用形態のスタッフが働いており、それぞれ働き方や待遇に特徴があります。代表的な正社員・パート・派遣社員について見てみましょう。
- 正社員(フルタイム)
正社員は事務所のコアメンバーとしてフルタイム勤務し、月給制で賞与(ボーナス)や昇給もある安定した待遇を受けます。担当クライアントを持ち、記帳から決算・申告書作成、顧客対応まで一通り任されるケースも多く、責任は大きいですがやりがいも得られます。
繁忙期には残業が発生することもありますが、その分経験を積んでキャリアアップにつなげることができます。中小事務所では外回り(巡回監査)と内勤を兼務し、大手では部署ごとに専門分野を担当するなど、事務所規模によって役割分担は異なります。 - パート・アルバイト
パートタイマーは短時間・週数日から働ける柔軟な働き方が可能で、家庭と両立したい主婦や資格勉強中の人にも魅力的な選択肢です。多くの事務所で「週3日・1日5時間」「午前中のみ勤務」といったシフトが認められており、自分の都合に合わせやすくなっています。
業務内容は税理士補助としてのサポート業務が中心で、仕訳入力や書類作成など比較的定型的な仕事が多い傾向です。その反面、給与は時給制で正社員より低めに設定されることが一般的で、地域にもよりますが相場は時給1,000~1,500円程度(都市部で~1,800円程度)と言われます。
ただ専門職の補助だけあって一般事務より高めの時給が提示されるケースもあり、経験やスキル次第では好待遇も可能です。またパートでも社会保険に加入できる事務所もありますし、扶養内勤務の相談に応じてくれる職場もあります。 - 派遣社員(契約社員含む)
即戦力人材を求める会計事務所では、派遣スタッフを活用する場合もあります。派遣社員は人材紹介会社等に登録して一定期間事務所で働く形態で、時給はパートより高め(東京都心では時給1,500~2,500円程度が相場)に設定されることが多いです。
派遣のメリットは、自分の希望条件に合った職場を紹介してもらえる点や、派遣会社が社会保険の加入手続きや有給管理を行ってくれる点です。週3日だけ働きたい、家から30分以内の職場が良い、といった希望に沿った案件を選べる柔軟性もあります。派遣期間を経て双方合意の上で正社員登用する「紹介予定派遣」の求人も増えており、未経験でも派遣から始めて正社員を目指す道も開けています。
なお、税理士の独占業務である税務相談や税務代理そのものは派遣社員には任せられないため、派遣スタッフはあくまで会計ソフト入力や資料作成など補助業務を担当し、専門判断は正社員税理士が行うという役割分担が一般的です。
このように雇用形態によって働き方はさまざまです。
未経験からフルタイムでじっくり経験を積む道もあれば、限られた時間でパート勤務して専門知識を身につける道、スキルを活かして高時給の派遣で働く道もあります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、自分のライフスタイルや目標に合わせて選ぶとよいでしょう。


リモートワークや柔軟な働き方の導入状況
業界の在宅勤務・フレックスタイムの採用動向
在宅勤務(リモートワーク)やフレックスタイムなどの柔軟な働き方は、会計事務所業界でも徐々に広がりつつあります。特にコロナ禍以降、ITツールを活用してテレワークを導入する事務所が増加しました。
例えば、データ入力や書類作成などの内勤業務は自宅でも対応可能なケースがあり、実際に「在宅勤務OK」を打ち出す求人も見られます。在宅勤務ができれば通勤時間を節約できるため、子育て中の方や遠方に住む方でも働きやすくなります。また、ある会計事務所では自宅用のサブモニターを支給し、自宅とオフィスでスムーズに業務が続けられる環境を整備している例もあります。このようにITインフラを整え、場所にとらわれない働き方を推進する動きが業界内で進んでいます。
勤務時間の柔軟性についても、多くの事務所で工夫が見られます。週3~4日勤務や1日5~6時間程度の時短勤務に対応している事務所は珍しくありません。実際、「子どもが小さいうちは10時~16時の時短勤務OK」「週2~3日在宅勤務可」など柔軟な条件を提示する求人も増えています。
さらに、繁忙期と閑散期で勤務日数・時間を調整する働き方も可能です。例えば確定申告前の2~3月だけ週5日フルタイムで手伝い、他の時期は週2~3日勤務に抑える、といったシフトを許容する職場もあります。
事務所による差
ただし、リモートワークやフレックス制度の導入状況は事務所によって差があります。
大手ではテレワーク制度が整備されている一方、中小事務所では「出社が基本」というところも依然あります。業務上どうしても紙の書類対応や対面での打ち合わせが必要な場合もあり、完全リモートが難しいケースもあります。しかし全体的な傾向として、人手不足への対策や職員の働きやすさ向上のために柔軟な働き方を模索する事務所が増えていることは確かです。



業界的にはまだまだ古い慣行が残っていることや、中小企業で紙文化が残っているクライアントが多かったりすると、どうしても紙を回収して入力してとなって、リモートでの業務が制限されるケースが多いのが実情です。
ちなみに、うちの事務所では、基本的に紙は禁止にして、クライアントからの書類の郵送も原則禁止ということで協力をしてもらい、デジタル化を推進してきたことから、全員がリモートで業務をできています。
子育てとの両立はしやすい職場?
「家庭と仕事の両立」ができるかどうかは、主婦の方にとって転職先を選ぶ重要なポイントでしょう。
結論から言えば、会計事務所は子育てと両立しやすい職場である場合が多いですが、その実態は事務所によって様々です。
パート勤務・時短制度の有無
まず、パート勤務制度や時短制度が整っている事務所では非常に両立がしやすくなります。前述の通り、週数日・短時間の勤務形態を受け入れる会計事務所は多く、保育園の送迎や学校行事に合わせて働ける環境が整っています。実際、会計事務所のパート職員として働くママさんは多数おり、「子どもの急な発熱で休みたい」といった場合でも同僚や上司が理解を示しフォローし合う文化が根付いている職場が多いようです。
ある事務所では「子育て中のママ社員が多く、お互い様の精神で急なお休みもカバーし合っている」といい、夏休みや運動会などの長期休暇・行事休暇も事前相談すれば取得しやすいとのことです。このように、家庭の事情に配慮してもらえる職場風土があるかどうかが両立のしやすさを左右します。
職場・規模による違い
一方で、職場ごとの違いも大きい点には注意が必要です。大半の会計事務所は中小規模で、所長(ボス)の考え方が職場の方針に直結します。
そのため「子育て優先で柔軟に働いていいよ」という所長のもとでは非常に働きやすいですが、逆に理解が乏しい職場だと肩身の狭い思いをする可能性もあります。
求人票の勤務条件をよく確認するのもポイントです。例えば募集要項に「10時~16時、週3日程度」と明記されていれば両立しやすい職場と考えられますが、フルタイム募集で「時短応相談」とだけ書かれている場合は、面接時に本当に時短実績があるか確認した方が安心です。
また、大手の税理士法人(Big4税理士法人や準大手クラス)ではほぼ例外なく産休・育休制度や時短勤務制度が整備されており、役割分担によるチーム体制もできています。特にテレワークを導入している大手法人では自分のペースで働けるため、制度上は子育てと両立しやすいでしょう。ただし「大手だから安心」とも言い切れません。業務量が多く残業が発生しがちだったり、制度があっても職場によっては遠慮があって利用しづらい場合もあります。実際に制度が運用されているか、育休復帰者がいるか、といった内情の確認も大切です。
まとめ
総じて、会計事務所は内勤中心で定時退社しやすい業務も多く、「子育て経験者が活躍している業界」と言われます。現に育休後に職場復帰して時短勤務で働く方や、子育て期間はパートで時短勤務しつつ落ち着いたら正社員登用される方もいます。転職にあたっては、ぜひ在籍社員の構成(ママさん社員の有無)や制度の利用実績についてもリサーチすると良いでしょう。
所長や面接担当者が子育てとの両立に理解を示してくれるかどうかも含め、自分に合った職場か見極めることが大切です。


働いている人の年齢層や男女比
男女比
会計事務所で働く人々の年齢層や男女比には、いくつかの傾向があります。一般的に、スタッフ職(補助スタッフや事務員)として働く人は女性が多い職場と言われます。
実際、とある税理士法人の例では社員の男女比がおよそ女性5:男性5でパートは女性が多数活躍しているというデータがあります。別の中堅事務所でも全従業員77名中54.5%が女性(45.5%が男性)と、公表されており、女性が半数以上を占める会計事務所も珍しくありません。特にパートや内勤スタッフは女性比率が高く、子育て世代の女性や主婦の方も多く働いています。
年齢層
年齢層については、スタッフの場合20代~40代が中心という事務所が多いようです。例えば前述の従業員77名の事務所では20代26%、30代19.5%、40代23.4%と、およそ70%が40代以下で構成されています。一方で50代以上のベテランスタッフも一定数おり、幅広い年代が混在しているのが特徴です。経験を積んだシニア層がパート勤務で後進をサポートしているケースや、逆に未経験から入った20代が先輩に教わりながら成長しているケースなど、世代を超えて協力し合っている職場も多いです。
資格をもつ会計士・税理士の場合
しかし、資格を持つ税理士・会計士層に目を向けると高齢化が顕著です。日本の税理士全体で見ると半数以上が60歳以上を占めており(2014年時点のデータ)、現在でも税理士の平均年齢は60代とされています。また税理士の男女比は男性が約85%、女性が15%程度と男性が多数派です。これは資格取得が難しく長年のキャリアを要するため、どうしても年齢層が高く男性比率が高かった歴史的経緯によるものです。
しかし近年は若手の女性税理士も増加傾向にあり、監査法人や税理士法人で女性が管理職に就く例も出てきています。業界全体としては経験豊富なベテランが多い一方で、そうした先輩方の指導のもと若い世代・女性も着実に活躍の場を広げていると言えるでしょう。
まとめ
要約すると、会計事務所は女性が働きやすい環境が整ってきており、20~30代から子育て世代、シニア世代まで様々な年代の方が混在している職場です。
主婦としてブランクがある方でも、同年代の女性スタッフが多ければ馴染みやすく心強いでしょう。また経験豊富な上司や先輩から学べる機会も多いため、異業種から飛び込んでも育っていける土壌があります。


小規模事務所と大手事務所の違い
会計事務所と一口に言っても、スタッフ数名の個人事務所から数百人規模の大手税理士法人まで様々な形態があります。それぞれ規模による特徴の違いがあり、仕事内容や職場環境、待遇面などに差が見られます。小規模事務所と大手事務所の主な違いを以下にまとめます。
- 業務範囲と役割分担の違い
大規模な税理士法人では部署やチームごとに担当業務が細分化され、各スタッフが専門分野に特化して働く傾向があります。例えば法人税申告チーム、相続税専門部署、コンサルティング部門などに分かれており、自分の担当領域の業務に専念する形です。
一方、小規模会計事務所では一人の職員が担当先企業の記帳から決算・申告まで一貫して対応する場合が多く、幅広い実務経験を積むことができます。極端な零細規模(スタッフ数名以下)の事務所では、所長税理士が外回り(顧客訪問)を行い、スタッフは内勤業務に専念するケースもあります。
顧客層も、大手は上場企業や外資系企業など大企業が中心なのに対し、中小事務所は地域の中小企業や個人事業主がメインといった違いがあります。 - 教育体制・人材育成
大手事務所ほど新人研修や教育制度が充実している傾向があります。Big4や大手税理士法人では、入社後に数週間~数ヶ月の研修プログラムが用意され、業務マニュアルやOJTによる体系的な指導が受けられます。資格取得支援制度など人材育成にも積極的です。
一方、小規模事務所では先輩や所長から直接仕事を教わるOJTが中心となります。マンツーマンで実務を学べる利点もありますが、事務所によって教え方や習得できる範囲が異なるため、教育環境はどうしても属人的になります。零細規模では新人教育に割く人手が不足しがちなため、即戦力の経験者を採用するケースが多いです。
ただ近年、「どこのカラーにも染まっていない未経験者を一から育てたい」という方針で新人を採用する所長もおり、未経験OKの小規模事務所も少しずつ増えています。 - 職場の雰囲気・社風
大手税理士法人は組織としてのルールや企業文化が整っており、社員の数も多いため比較的ドライでビジネスライクな人間関係になりやすいです。評価制度もしっかりしていて、成果に応じて昇進・昇給していく企業的な風土といえます。
これに対し、小規模・個人事務所は所長の人柄や経営理念が職場の雰囲気に直結します。所長が従業員を家族のように大事にする人ならアットホームで温かい職場になりますが、ワンマンタイプで厳しい人だと緊張感のある職場になる、といった具合です。実際「個人会計事務所は所長が裸の王様になりがち」との指摘もあり、所長の方針次第で働きやすさが大きく左右されます。
したがって小規模事務所を志望する場合は、所長や先輩スタッフの雰囲気を事前によく観察し、自分に合いそうか見極めることが重要です。 - 働き方の柔軟性
大手税理士法人は前述のように働き方改革が進んでおり、産休・育休制度や時短勤務制度、テレワーク制度などが整備されています。組織として人員のバックアップ体制もあるため、長期休暇の取得や部署間のヘルプも比較的スムーズです。
小規模事務所でも最近はIT化に取り組みテレワークを導入する例が出てきましたが、制度面は事務所ごとにまちまちです。柔軟な働き方ができるかどうかは、その事務所のスタッフ構成や所長の理解度に依存するでしょう。「スタッフ数に余裕がなく一人でも欠けると回らない」ような零細事務所だと在宅勤務は難しいですが、逆にパートやママさん社員が多い事務所では子どもの都合最優先で働けるルールを設けている例もあります。
このように規模により事情は異なりますが、自分にとって無理なく働ける環境かどうかを見極めることが大切です。 - 給与・待遇面
一般に規模の大きい法人ほど給与水準や福利厚生は高めと言われます。Big4税理士法人では残業代込みで年収800~1000万円以上も珍しくなく、中堅以上でも資格保有者なら安定した高収入が期待できます。
一方、中小の会計事務所は年収ベースでは大手より低めになりがちです。ボーナスが無かったり退職金制度が無い事務所も多く、昇給幅も小さい傾向があります。その代わり残業が少なかったり通勤圏内の地元企業であったりと、待遇以外の魅力を打ち出す事務所もあります。また、人件費を抑えるためパートスタッフを多く活用している事務所もあります。
ちなみに時給相場を見ると、前述の通り都市部ではパート時給1,100~1,500円程度なのに対し、派遣では1,500~2,500円程度と差があります。このような相場感も事務所規模や求めるスキルによって変わってくるでしょう。
以上のように「大手か中小か」で職場の実情はかなり異なります。それぞれメリット・デメリットがあり、どちらが良いかは一概に言えません。
大手の魅力
研修制度が整いキャリアパスが明確なことや待遇の良さ、専門分野のプロになれることです。反面、組織が大きい分歯車の一部になりやすく、クライアントとの距離が遠い・業務がルーチン化しやすいという面もあります。
中小の魅力
経営者に近い立場で幅広く実務経験を積めることや、アットホームで柔軟な働き方ができる場合があることです。その代わり人によっては成長機会が限定的だったり待遇面で物足りなさを感じることもあります。
転職の際は、自分が重視するポイント(専門性を磨きたいのか、プライベートと両立したいのか等)に照らして、規模ごとの特徴を考慮すると良いでしょう。
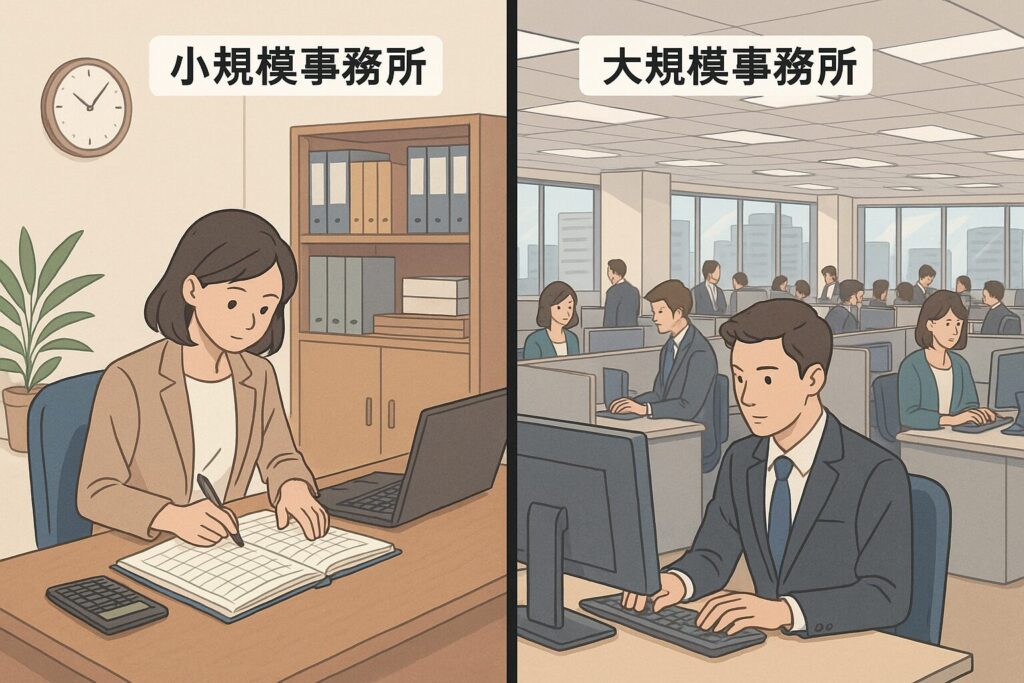
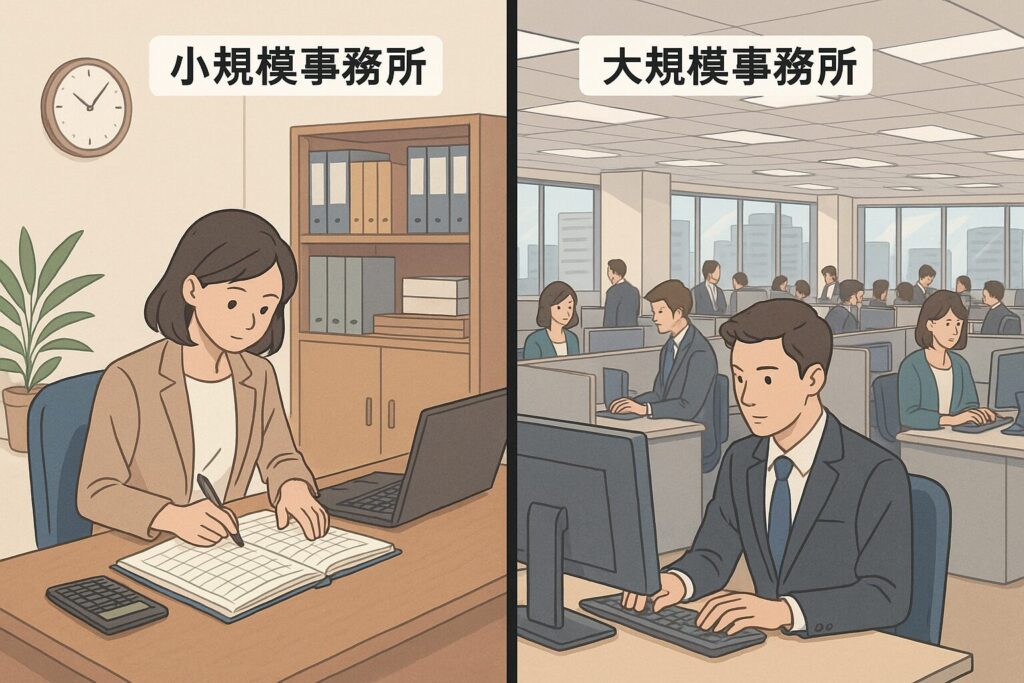
業界の将来展望:人手不足時代をどう乗り切る?
最後に、会計事務所業界の将来展望について触れておきます。
5年後・10年後の展望
結論から言えば、人手不足の傾向は今後5年・10年でさらに顕著になると予測されています。少子高齢化による労働人口減少は避けられず、税理士試験合格者の高齢化も進んでいるため、現状のままでは即戦力人材の不足が一層深刻化していくでしょう。TKCグループのレポートでも「5年後・10年後には構造的な人材不足がさらに進行し、会計事務所は深刻な人手不足の時代に突入する」と警鐘が鳴らされています。
しかし、これは裏を返せば新たにチャレンジする人にとってチャンスが広がることも意味します。人材が不足する分、業界未経験者やブランクのある人を歓迎し育成しようという事務所が増えているのです。事実、ある税理士法人では「スタッフの約9割が未経験スタート」で新人研修を充実させているとのことで、未経験者の積極採用と育成は業界全体の課題かつ重要な取り組みとなっています。



うちの事務所も15名程度の規模ですが、基本的には未経験者を採用して育成するスタイルをとっています。
もともとは他の会計事務所の待遇に勝てず経験者採用が難しかったことから、未経験者採用・育成の路線を推し進めましたが、今となっては「変な癖のついていない未経験者」の方が成長余力が大きく、戦力に育ってくれています。
国税庁も税理士試験制度の見直しや働き方改革による人材確保策を検討しており、業界団体も若手・女性の入業支援に乗り出しています。今後はシニア層や主婦層の活用もカギとなるでしょう。実務経験豊富なシニア税理士に在宅で顧問業務だけお願いしたり、フルタイム勤務が難しい有資格主婦にパートで決算書チェックを手伝ってもらうなど、柔軟な登用が人手不足解消に役立つとの指摘もあります。
AI活用の時代におけるヒトの役割
さらに、テクノロジーの進展も業界の姿を変えていく可能性があります。AIやRPAの導入によって記帳や経費精算など定型業務の効率化が進めば、職員一人あたりの業務負荷軽減が期待できます。一方で、AIでは対応しきれないコンサルティング業務や高度な判断業務の需要はむしろ増加すると見られています。
実際、財務分析や経営アドバイスといった領域ではAIを活用しつつも最終的な判断や顧客対応は人間の会計士・税理士が担うケースがほとんどで、そうした付加価値の高いサービス提供に人手を回せるかが競争力の鍵となるでしょう。
要するに、「人」と「技術」の両面から変革を進めていくことが業界の課題であり希望でもあると言えます。人材の確保と育成、業務の効率化、そして働きやすい環境の整備は、いずれも会計事務所の未来を明るくする重要な要素です。実際にこれらに取り組むことで「人手不足を解消し事務所を成長させている」事例も出てきています。
例えばクラウド会計やチャットボットを導入し業務時間を削減しつつ、空いたリソースで職員研修を行ってサービス品質を向上させた事務所もあります。また地方の小規模事務所同士がオンラインで人材をシェアし繁忙期を乗り切る試みなど、新たな動きも生まれています。
業界未経験の主婦の方にとっても、チャンスは充分にあります。
人手不足の業界だからこそ、意欲があり学ぶ姿勢のある人材は歓迎されやすい側面があります。実際「未経験者でも簿記の知識があれば採用したい」という求人も増えており、家計簿程度の経験しかなくても簿記検定の勉強から始めて会計事務所デビューしたという例も珍しくありません。大切なのは、新しいことを積極的に学ぶ姿勢と丁寧に正確に取り組む姿勢だと現場の声もあります。最初は覚えることも多く戸惑うかもしれませんが、周囲のサポートを受けながら経験を積めば着実に成長できるでしょう。
まとめ
会計事務所業界は現在、人手不足という課題に直面しつつも、その解決に向けて働き方の見直しや人材育成、新技術の活用など変革が進んでいます。主婦の方でも働きやすい柔軟な職場が増えつつあり、今後も「人」を大切にする職場ほど生き残っていくと考えられます。
経理・会計のスキルは一度身につければ一生ものの財産です。
業界未経験でも興味があればぜひ一歩踏み出し、あなたの力を必要としている会計事務所を探してみてください。きっとあなたの経験や強みを活かせる職場が見つかることでしょう。業界の現実を正しく理解し、自分に合った働き方を選ぶことで、家庭と仕事の両立を実現しながら新たなキャリアを築けるはずです。皆さんの転職検討の一助になれば幸いです。



